黄金の薔薇 第7話
百日の薔薇 クラウス×タキ×クラウス クラウス女体化
アクア版1巻、2巻ベースでオリ設定があります。
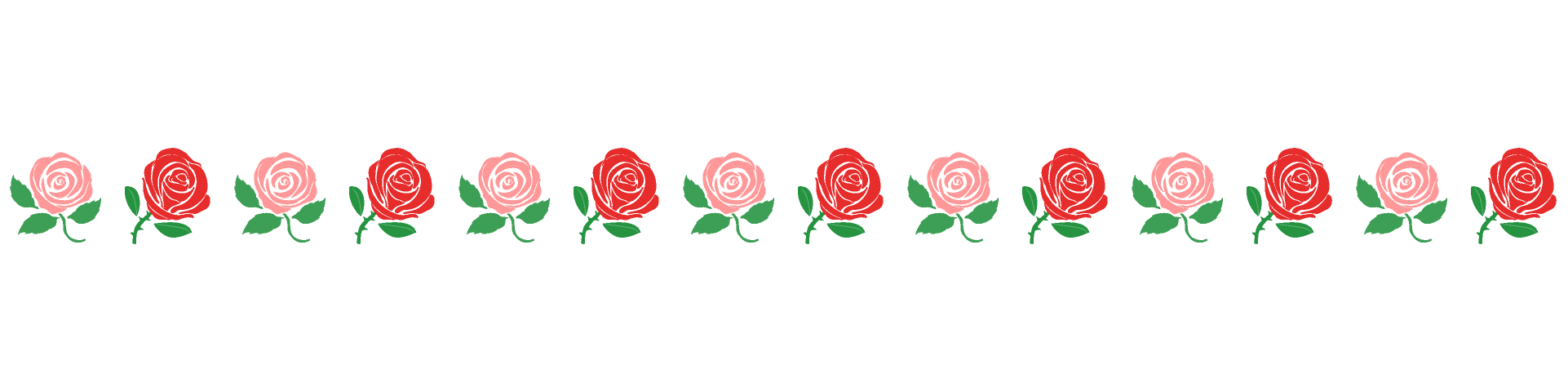
クラウスの腕に刺された注射針の先から血が抜かれ、透明な容器が赤く染まっていく。
「詳しい症状は、血液検査の結果が出てからです」
アンプルを収納鞄に詰めながらスグリが告げる。
「検査には半日ほど要します」
「わかった。かならず症状を見つけてくれ」
ベッドサイドに置かれた椅子に座り、クラウスの手を握りしめ容態を伺いながら
タキは告げる。
「あのタキ様・・・」
部屋の隅で様子をうかがっていたハセベとウエムラ少佐が話しかける。
「クラウスが起きる。司令室で聞こう」
タキは信頼がおく人間として女官長とハルキに後を頼み、部屋を出た。
司令室にて、タキはハセベ、ウエムラ、情報部と憲兵隊それぞれから話を聞いた。
「憲兵隊がクラウスを拘束しようとしたそうだな」
「はい。彼女にはスパイ疑惑が持ち上がりまして」
「根拠は?」
タキの質問に情報室長が新聞をテーブルの上に上げる。
「これはハルキ士官候補生の証言によりクラウス大尉の物であると判明したバック
パックから見つかった物証です」
「これか」
タキはそれを一瞥しただけで一蹴した。
「ただ新聞を持っていただけでなぜスパイとなる。おまえ達も向こうの戦況を知る
ためにルートを使って新聞を取り寄せているだろう」
「それは確かに」
「ですが、なぜ情報部でもないクラウス大尉がこれを取り寄せていたのですか」
「決まっている。私が命じたからだ」
タキの言葉にその場にいた全員が唖然とした。
「タ、タキ様がですが?」
「そうだ。彼女は私と出会ったときは酒場で働いていたが、それ以前は航空機部隊
で小隊長をつとめていた。家も代々続く貴族の家で政財界にツテも持っている。そ
れから戦況を探れと私が命じたのだ」
騎士選考の素性調査で、場末の酒場で働いていたことからクラウスは、どこの馬
もしれぬ女と思われていたが、由緒ある古い家系の貴族の当主の娘であり、兵役に
も就いていた事実が判明し選考委員を驚かせた。
「で、ですがこれはどうですか」
情報室長は、もう一つの物証である手紙を取り出す。
「これには、我が国との戦況が事細かく記載されています。しかも手紙を書いたのは、
むこうの情報部長ですよ。これはどう説明なさるおつもりです」
むこうの情報部長ですよ。これはどう説明なさるおつもりです」
タキは、手紙を受け取ると内容を一読する。
そして、なにやら考え込んだがこれもパサリと投げ捨てるようにテーブルに戻し
た。
「これも心配いらない。この手紙を書いた人物は、クラウスの養父だ」
「ええ!?」
「昔、家族といざこざを起こして、家を出ていた時期が合ったらしい。そのとき面
倒を見ていてくれたのが彼だそうだ」
「で、ですが・・・」
「その人は、クラウスの実母の知り合いらしい。素性ははっきりしている。何より
私も何度か会っている」
「ええ!?そうなんですか?」
意外な事実に一同は動揺を隠せない。
「当然だ。彼はルッケンヴァルデ機甲機工学校の学長だからな」
もういいだろうとタキは、唖然としている一同を残してクラウスがいる部屋へと
向かった。
***********
日が落ちて一気に気温が下がる。
部屋には暖炉がともしてあるが、ここは雪も降る寒冷地帯だ。底冷えも酷い。
タキは、毛布をとってきてクラウスにかけてやるが、クラウスは心なしか震えて
いた。
「クラウス。寒いのか?」
クラウスにはすでに3枚の毛布を掛けてある。これ以上枚数を増やすのは重いだ
けだろう。
仕方がないと、タキはクラウスの寝ている布団の中に潜り込むとクラウスを抱き
しめた。心なしか手足が冷たい。女性に冷えは大敵だと、義母に仕える侍女達が
言っていたのを耳にしたことがある。
「クラウス、大丈夫だ。私の熱をすべて奪ってしまえ」
タキはクラウスの手に手を絡ませた。
その頃、エウロテ東部より皇国に向かって走る列車があった。
「いかがでした晩餐会は?」
晩餐会が開かれていた部屋の入り口から男が中にいる女に話しかける。
「退屈なものだったわ」
女は周りに転がる死体に眉一つ動かさず、平然としていた。
「でも、あなたは楽しそうね」
「なんでしょう。予感って奴ですかね」
「予感?」
男の言葉に女はくすりと笑った。
「それはいい予感なの?」
「ええ。全身の血がたぎるほどのね」
夜が明ける3時間前のこと。
仮眠もとらずクラウスを暖め続けていたタキは、ハセベとウエムラの訪問を受け
た。
ハゼとウエムラは二人の状況に眉をひそめたが、それを上回る緊急事態なため、
ここは目をつぶり、用件に入った。
ここは目をつぶり、用件に入った。
「何事だ?」
「はっ。実は・・・」
二人は、エウロテからの進入列車について報告した。
「このままいくと中間地帯を通り、わが領内に進入します」
「識別はできているのか」
「「RYT]。王族の列車です」
「エウロテとの交信は?」
「すでに行いました。ですが返答はまだありません。本国の方にも行いましたが、
こちらも同じです」
「5分で支度する。情報将校を司令室へ集めてくれ」
タキは、ベットから起き上がった。
タキが去ったあと、彼女が目を覚ました。
西方諸国連合からの帰国の列車の中での出来事だった。
『タキ、あっちの線路は?』
クラウスが指さした線路はすぐに草原の中に消え去った。
『あのあたりは中間地帯だ。前の大戦随一の激戦地帯で、エウロテとの条約により
誰も足を踏み入れられぬ地となった』
我等が祖先が眠る大地とタキは言った。
『私は必ずあそこを取り戻す』
『大丈夫よ、あたし達二人ならきっと』
必ず取り返し、彼の地を二人で歩もう。
それは誰も知らぬ二人だけの約束であった。
「注視」
司令室。司令官席に着席したタキは、くだんの侵入列車についての対策を検討し
始めた。
「参謀部は、アサクラ総司令との直接回線を開け」
「先ほど要請していますが、就寝中を理由に拒否されています」
「開くまで続けろ。本国総司令部の応答は?」
「それが、今回の件は内・外務省両省との折衝をしながら対応するとのことで、
独断専行は慎むべしと」
『東洋人は、突発的自体に対応することがきわめて不得手である』
向こうで聞いた皇国の評価が的を射ていたことを、タキは改めて思い知らされた。
走行している間にも列車はどんどん領内を侵入していた。レールの状況が芳しく
ないため、速度は遅くなったものの止まる気配はない。
せめて詳細な報告がほしかった。
しかし、頼みの綱のタチバナ領航空部隊からの返事もつれないものであった。
「すまんが、偵察機を含む航空機は一切飛ばせない。不浄の地の触ったとあれば隊
の存続に関わる」
「我が霊地を愚弄する気か!?」
「そういうわけでは聞け」
タチバナは電話口から諭す。
「落ち着け、今回の件は内・外務省が絡んでる。となるとあいつが絡んでこない
はずがないんだ」
あいつと言われ、タキは奥歯をかみしめる。
「あいつは昔からおまえを敵視してきたから。それ加え、おまえは女性の騎士を
持った」
「・・・・あれが私を嫌っていることは知っている。だが、それとクラウスと何の
関係がある」
「そうか、おまえは知らないんだな。無理もないか。もう25年も前の話だ」
あの頃を知る者の大半は、前の大戦で黄泉路へ下り、残っている者で彼女の存在
を覚えている者は少ない。
「あいつもな女性の騎士持ってたんだ。あいつの騎士が、この国始まって以来
初めての女性の騎士だったんだよ」
本国大極殿・内務省。
その一室からレイゼン方面の空を見つめている男がいた。
「カツラギ内務副大臣。外務省より入電です」
「政務次官に回したまえ」
カツラギの指示に、入電を持ってきた秘書官は従い政務次官室に向かった。
「あなたは、今回の問題には介入されないのですか?」
室内のソファに腰掛けた男が話しかける。
「あなたが動けばすぐに解決するでしょうに」
「私の出番は、まだ先ですよ」
カツラギは、窓の外を眺めながら答えた。
「・・・・・薔薇の師団長はどうしているでしょうね」
「今はまだ大人しくしているようですが」
「そうですか。いつまでもつでしょね」
「いずれ動き出すと?」
「当然でしょう。彼は誇り高い男だ。領内が黙って蹂躙されようとしているのを
見過ごすことなどない」
信頼しているからこそカツラギは待っているのだ。タキ・レイゼンが動き出すこ
とを。
彼が動き出したとき、カツラギが用意した舞台の幕が開けるのだ。
「恐ろしい方だ」
男は、参ったと顔をゆがませる。
「そうそう。邪魔になる予定のレイゼンの騎士ですが、彼女、倒れたそうですよ」
ここで初めてカツラギは男の方を振り向いた。
「倒れた?」
「ええ、潜入させている者からの報告です。なんでも拘束しようとした憲兵の顔に
向かって嘔吐したあげく倒れたとか。気の毒ですよねぇ。だいたい女が騎士なんて
無理なんですよ。まぁ、こちらの手間が省けて助かりましたが」
ハハハッと笑いながら出された紅茶をすすっていた男は、カツラギが冷ややかな
目をしていることに気がつかなかった。
PR
